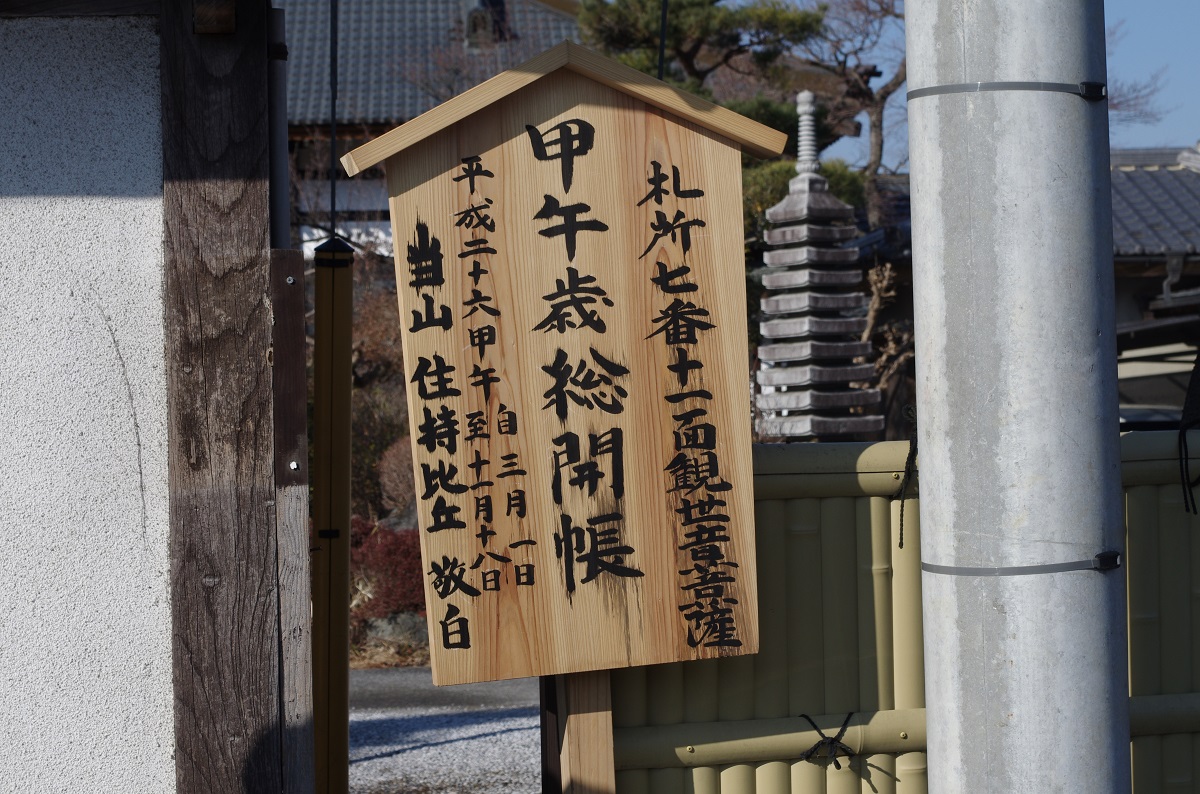秩父巡礼 2回目
横瀬駅 → 6,7,8,9,10,11,12,13,16,14,15 番札所 → 西武秩父駅
2014.01.22(水)
秩父巡礼 2回目
横瀬駅 → 6,7,8,9,10,11,12,13,16,14,15 番札所 → 西武秩父駅
2014.01.22(水)
昨年の1回目は、東武東上線小川駅で下車し、橋場バス停より、 標高 560m の粥仁田峠を越えて1番札所に入り5番までを順次に歩き、 横瀬駅から帰途につき、総歩数4万歩(約25km)だった。
2回目は6番からとなるが、横瀬駅から6番に向かうと、どうしても 次の7番・9番までの道が同じ道を引き返す事になりなんとなく 面白くない。そこで地図を見ていると、西武線 芦ヶ久保駅(標高 300m) からあしがくぼ果樹公園村を通り、琴平神社(530m)まで登り6番(250m) にたどり着く山道を、昭文堂発行の「奥武蔵・秩父」に発見した。
しかしそうすると、5番と6番の間が断線となってしまう。やはり 横瀬駅より前回の中断したところまで戻り、そこから巡礼道を 連続することにした。こうすれば、同じ道を引き返す事もない。
前回同様、朝早く起き、水海道 5:45 --> 守谷 6:00 --> 南流山 6:19 --> 新秋津 7:07 --> 西武秋津 7:19 -->飯能 7:53--> 横瀬 8:38 に到着し、 駅前を見渡すと前回の風景がよみがえってきた
西武線 横瀬駅 左のほうに武甲山が見える

足取りを辿り、ここが前回の別れた三叉路地点